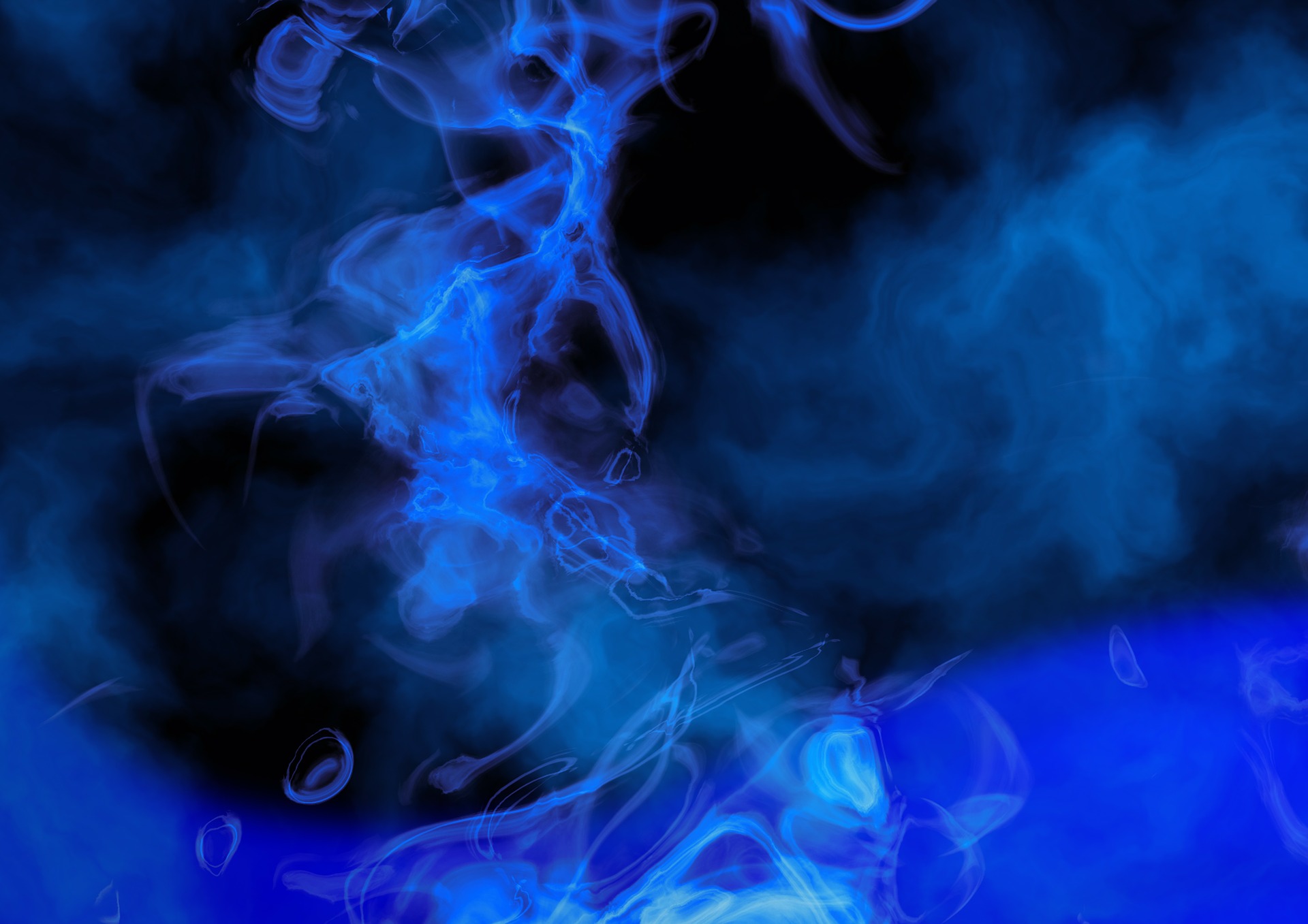フランク・シナトラを聴くときに欠かせないもののひとつは、シナトラ本人と歌はもちろんですが、曲のアレンジとバンドやオーケストラの演奏でしょう。
シナトラのアレンジャー達に対する敬意や、アレンジャーが半分プロデューサー的な要素を兼ねていたことを考えると、シナトラを聴くということは、シナトラとアレンジャー、オーケストラの「組合せ」を聴いていると言っても良いと思います。
またJAZZやアメリカのポピュラー音楽の楽しさは、同じ曲を、沢山の違う歌手やプレイヤー、そしてアレンジャーが様々に違うアプローチで演奏することにもあり、むしろそのことで、差・違いとしての個性が際立つ訳です。
もちろんシナトラの録音や作品にもそういう要素が多くあるように感じています。(シナトラの場合はシナトラが他の歌手やプレイヤーの基準になってしまっているとこともありますね。笑)
At Long Last Love
「At Long Last Love」というコール・ポーターの曲があります。
シナトラとコール・ポーターと言えば、「Night And Day」、「I’ve Got you Under My Skin」、「I get A Kick Out Of you」など、ステージでも必ず歌う“お決まり”も含めて数十曲の録音があり、いくつかのアレンジのバージョンで録音しているものもあります。「At Long Last Love」は、コール・ポーターの他の曲に比べるとあまり有名でないかも知れませんが、長めで複雑な曲が多いコール・ポーターの作品の中では、シンプルな短めの曲で分かり易いものです(歌詞を除けばの話:笑)。
そしてシナトラは、この「At Long Last Love」を違うアレンジのバージョンで2回、CapitolとRepriseで正式に録音しています。それぞれのアレンジャーは、ネルソン・リドルとニール・ヘフティです。
ご存知ネルソン・リドルとシナトラは、Capitol~Repriseまで長い間、名コンビとも言うべき沢山のアルバムがありますが、ニール・ヘフティとのアルバムはReprise時代に2つあります。
十数人いるシナトラのアレンジャーの中で、ネルソン・リドルとビリー・メイ、ドン・コスタを除くと、他のアレンジャーとのアルバムは1つ~3つくらいです。
もちろん、どのアルバムとコンビも素晴らしく優劣などはあまり決められないものですが、楽器や編曲をかじっていた僕個人としては、ニール・ヘフティとのアルバムをものすごく気に入っています。
この時代は、歌手とアレンジャーとアルバムは基本的にセット=作品なので、僕にとっては“シナトラを聴く“とは、例えば、まさに、この”組合せの仕事”そのものを追体験することと同じな訳です。
そこで今回は、シナトラとは切り離せないコール・ポーターの分かり易い曲で、アレンジや演奏の違い、シナトラの歌い方などの点で、僕の「シナトラ体験」としての聴き方をご紹介するのに一番ぴったりな、この「At Long Last Love」と2つ録音を取り上げたいと思います。
コール・ポーターと「At Long Last Love」の関係
シナトラの曲のアレンジの話の前に、コール・ポーターと「At Long Last Love」について触れなければなりません。
1938年のブロードウェイ・ミュージカル、「YOU NEVER KNOW」の音楽をコール・ポーターが担当し、その中の約30曲の中で、唯一、後日取り上げられて有名になった曲です。
コール・ポーターの曲
コール・ポーターの曲はJAZZ、ポピュラー音楽のスタンダードとなっていますが、その中では比較的に1曲(1コーラス、1番目部分)が比較的長く、また少し変則的なところもあります。
簡単に言うと、普通だいたいスタンダードの1曲の長さが標準的に32小節(楽譜上の一単位)だとすると、コール・ポーターの有名な曲は64小節が結構あり、長いです。
例えば「I get A Kick Out Of you」や「Just One Of Those Things」、「Begin the Beguine」です。
また「Night And Day」は48小節、「I’ve Got you Under My Skin」は56小節で、32小節を例えば基準とすれば、12小節や24小節分長く、また変則的です。
しかも曲の中でのパートごとの雰囲気も(例えばAメロやサビなど)何種類かあったり変わっていくことが多いし、逆に基本のパターンを少しずつ変えながら変化させていく場合もあります。
これは、歌いたく演りたくなる大曲なのですが、演奏する側からするとやりづらく、作りにくいところがあります。
要するに32小節でサビが1つだと、起承転結的な流れが分かり易く、掴み易いのですが、長めで構成や変化が多いと若干取っ付きにくい訳です。
でも「At Long Last Love」は32小節で、前にも言いましたが、比較的分かり易いものだと思います。
またコール・ポーターの曲のコードとコード進行や音階(ドミソの和音と変化のさせ方、音の上昇・下降の使い方)は、もちろん彼の場合はオーケストラのスコアを書くのではなく、元となる基本形として原曲が書かれているだけなので、ワーグナーやシェーンベルク、スティービー・ワンダー、ビル・エヴァンスほど取り立てて複雑ではなくベーシックなものですが、特徴的な、と言うか、おそらくコール・ポーター本人が好きな進行と転調のパターンがあり、マイナー(悲しい感じ、短調)の響きが出るように作られています。
ちなみに、いろんな人の感想を聞いたり、ブログや本を読むと、コール・ポーターはマイナー調の曲が多いという話が出ますが、音楽的には代表曲はメジャー(明るい感じ、長調)の曲の方が多いです。
つまり、音楽的にマイナー調の曲を書いている訳ではなく、基本的にはメジャー調の曲で、コードの進行や転調、メロディーに使う音階の流れ、途中で部分的に変化を付けるコードが、“マイナーな感じに聞こえさせている”ということです。
JAZZに定義があるとすれば、その重要なひとつの要素は“Blue Note”(古典的な西洋音楽的には不協和音、JAZZ、ポピュラーではちょっと悲しい感じを出す音の意味で)ですが、音楽の歴史から捉えると、それをどのように西洋音楽の理論やポピュラー音楽の雰囲気の中に組み込むかが作曲家の違いであり、それをどう演奏に盛り込んでいくかがアレンジャー、プレイヤーの個性・特徴となっています。
コール・ポーターは、彼自身のやり方で、まさにその“ちょっとブルーな感じ”を出そうとする仕掛けを曲の中に仕込んでいて、それがJAZZぽさと、彼の独特の個性を生み出している要因なのだと思います。
そんな中で「At Long Last Love」は、一部分を除いてかなりシンプルで単純です。
後に書きますが、それこそが、コール・ポーターらしさであり、この曲がシナトラやアレンジャーに選ばれる理由ではないかと思います。
コール・ポーターのワードチョイス
コール・ポーターの歌詞もどこか独特です。よく言われる通り、皮肉ぽく、音楽的な要素も相まって都会的な感じがしますが、加えて言えば、何より彼の歌詞が理屈ぽく、抽象的で、心の中というか半分以上は頭の中での思案、多角的な視点からの思考シミュレーションのように感じることが多いです。
「Begin the Beguine」を聴いても、ビギンを踊りたいようには聞こえないし「I love you」を聴いても、目の前に好きな人がいるようなサウンドではないですよね。愛がテーマ、トーチ・ソングであれば、大概そのようなものかも知りませんが、使われるワードや論理の展開を聞いていると、驚いてしまうし、愛より恋なのだなと思うのと同時に、純粋ながらも理屈ぽい人格があるような気がしてそれがシナトラっぽさでもあると感じています。
ただ「At Long Last Love」は、さらに特徴的で一見(一聴?)意味不明だと思います。
歌詞と文章のほとんどは疑問形で、「is it ~~~?、or is it ~~~?」の延々の繰り返しです。
しかも出て来る言葉は、もちろん“愛と記憶のメタファー“だとは思いますが、すべて具体的なモノや地名<例えば、地震、亀のスープ、カクテル、グラナダ、アズベリー公園>です。
なにより日本人の経験や習慣からすると(おそらく今のアメリカ人からしても多分一部の人はおそらく)はっきりとは分からないようなものだと思います。
また2つのセンテンスごとに最後のワードがきちんと韻=rhymeを踏んでいます<例えばearthquakeとshock、larkとpark、~~ thinking ofとAt Long Last Love>。
そして題名の<At Long Last Love>というワードは最後に出てきます、しかも疑問形のままです。 <The real MaCoy>というワードが前半部分の最後に出てきますが、これは「正真正銘の本物」と言う英語の慣用句らしいのですが、その意味からすると、この曲の核心はこの部分にあるはずです。
要するに、ミュージカル自体は別として、「At Long Last Love」は、時代と彼のセンスにあったワードを選びつつも、本物はどこにあるのか、何なのか、ということで、ワードはなんでも良かったのかも知れません。
なお、コール・ポーターは作曲と作詞を1人でやりました。ミュージカルやスタンダードの曲はだいたい作曲と作詞は別の人がやりコンビで作られることが多いです。
この「At Long Last Love」は、コール・ポーターらしい理屈っぽい疑問形~の歌詞が、シンプルだけども少し変化していく曲にあわせて最後まで繰り返され、後半に向けて一体となって盛り上がっていく特徴的な曲ですが、これは1人で作曲と作詞をやっているからこそ、作れるような気がします。
おそらく2人のコンビでこういう曲を作るのは、意見が合わずケンカしてしまいそうで、作れる気がしません。
そこがまさに、愛されるシンプルさと歌いたくなってしまうほどの魅力を出しているように感じますし、スタンダードとして取り上げられ続ける理由かも知れません。
シナトラの「At Long Last Love」を聴く
ここからは、シナトラの2つの録音のアレンジと演奏、シナトラの歌について、僕の「シナトラ体験」を書きます。Repriseの「At Long Last Love」を軸に聴きながら、Capitolの「At Long Last Love」と聴き比べ、時折、シナトラの他の録音・録画や他の歌手・アレンジャー等についても触れたいと思います。
2つの「At Long Last Love」とアレンジの構成
R/ヘフティ版
Reprise時代のアルバムは『Sinatra and Swingin’ Brass』で、1962年の録音です。
シナトラはRepriseの設立直後で、脂の乗った47歳です。
このアルバムには全12曲(初回のレコード版)が収められており、コール・ポーターの曲は3曲あり、そのうちの1曲になります。
やはりこうして見るとコール・ポーターが多いですね。
アレンジャーはニール・ヘフティです[以下、このバージョンは「R/ヘフティ版」とします]。
C/リドル版
Capitol時代のアルバムは『A Swingin’ Affair』で、1957年の録音です。
シナトラはCapitol全盛期の42歳です。
このアルバムは全15曲(初回のレコード版)で、コール・ポーターの曲は4曲、そのうちの1曲です。
やはりまたコール・ポーターが多いですね。
アレンジャーはネルソン・リドルです[以下、このバージョンは「C/リドル版」とします]。
「At Long Last Love」解説
「At Long Last Love」は前にも触れたように32小節です。
この曲は、曲調や歌詞から見て、8小節単位で4つのパートから成り立っていて、「A – B – A+ – C」にの4つに分けられます。
そして<is it an earthquake ~ real MaCoy>までの“前半”の「A」と「B」、<is it for all time ~ at long last love>までの“後半”の「A+」と「C」でさらに大きく括ることができます。
「A」と「A+」で分けたのは、半分似ているのですが、盛り上がる「C」に向けて「A+」の終わりのコード進行が変化しているからです。
2つの編曲全体の構成は似ています。
どちらの版も1コーラス(32小節:「A – B – A+ – C」)を2回繰り返し、要するに歌詞は同じですが1番と2番を歌う形です。
そして「R/ヘフティ版」では、①録音時間は2:15、②小節数は全部で74小節(イントロ4、本編1-2番で64、エンディング6)、③調・キーは1番がBb、2番がBで転調(♪ドレミファ~のシのフラットからシ)、④テンポ(♪速さ)は少し早めのミディアムです。
「C/リドル版」では、①録音時間は2:19、②小節数は全部で76小節(イントロ8、本編1-2番で64、エンディング4)、③調・キーも同じ1番がBb、2番がBで転調、④テンポは同じくらいの少し早めのミディアムです。
③の調・キーに関連し、この曲のメロディーの音域のレンジですが、1オクターブと少しくらいで広くなく、あまり高低もありません。
なので比較的歌い易いです。またこのシナトラのキーだと、一番下の音がC(ド、ヘ音記号の下の部分)で一番上が転調後のD#(レ#、ヘ音記号の上に飛び出た部分)です。
シナトラはあまりメロディーのアレンジや即興をやらないので、歌い方は別として、メロディー・ライン自体は原曲に近いです。ただ個人的には、シナトラはFやG(ファやソ)くらいまで出ますので、「R/ヘフティ版」では、もう1つか2つほどキーを上げたバージョンを聴きたいなと、いつも考えてしまいます。
後でテンポとあわせて触れますが、2回目の「R/ヘフティ版」では、もちろん1回目の「C/リドル版」の録音と同じキーがよいという理由が大きいはずですが、元々はもっと遅いゆっくりしたテンポであったと考えられ、おそらくニール・ヘフティが、この個性的な歌をよりレイジーでジャジーな雰囲気でやりたかったので、シナトラの太目の声がストレートに出る音域で同じキーのままにしたのではないかとも思います。
そして④のテンポです。確かにどちらも結果としては同じテンポとなっていますが、「R/ヘフティ版」の“メイキング録音”を聴くと、だいぶ事情が違います。このメイキングでは、最初の1テイク目と2テイク目のテンポがこの3分の2くらいで演奏されており、かなり遅いのです。
でもよくよく聴いてみると、この遅いテンポも、曲と歌詞の雰囲気と合い、シナトラのリラックスした中低音が響き、良い気怠さのある仕上がりに聞こえます。
気のせいかも知れませんが、バンドも遅いテンポの方が吹き方もやさしく音も小さめですし、シナトラもテンポが理由というよりは、歌自体の雰囲気をソフトにさせています。
ところが、突然3テイク目になると、テンポが変わります。
アルバムで使われているバージョンの少し早めのミディアムです。
メイキングを聴いていると、どうやらこのテンポはシナトラが指示しているようです。
シナトラが指のスナップやバンドの伴奏を声で出し、テンポとノリを示しています。
そしてこの3テイク目は、完全にテンポを全員で確認するテイクとなっていて(シナトラがほら!いくぞ!と発破をかけてますし、エンディングでふざけて歌っています)、その後4テイク目と5テイク目の2テイクを録ったようですが、メイキングでは3テイク目までしか入れてないので、おそらくアルバムに採用されたのは4か5テイク目だと思います。
しかし、おそらくニール・ヘフティは、テンポが変わったことは、ちょっと嫌だったのではないでしょうか。
と言うのは、別で触れたい内容ですが、この『Sinatra and Swingin’ Brass』のアルバムに入っている曲は、「At Long Last Love」も含めて大部分を、ニール・ヘフティが選んでいます。もちろん、ネルソン・リドルが5年前にCapitolで録音したことを当然知った上で、彼はあえて「At Long Last Love」をピックアップしているので、もしかすると、雰囲気の違う「At Long Last Love」を作りたかったのかも知れないからです。でも、テンポは同じになってしまいました。
ただアレンジもシナトラも時代も違うので、聴いている方としては、どちらも違うものとして楽しく聴くことができます。
また、この「At Long Last Love」が早目のテンポになってしまうと、このアルバムでゆっくり目の曲は「Serenade In Blue」くらいになってしまいますので、アルバムの曲のバリエーションや構成上、もう1-2曲はゆっくりなテンポの“スウィンギン・ブラス”を聞かせたかったはずだからです。
もちろんいずれにしても、逆に「Serenade In Blue」がより浮かび上がって忘れがたい1曲となり、何よりシナトラらしい「At Long Last Love」が、もう1つ、作られたのではないかと感じます。
ビッグバンド/オーケストラの編成
続いて「At Long Last Love」の2つのアルバム・録音バージョンでのオーケストラ/ビックバンドの編成についてです。
先に古い方の「C/リドル版」ですが、記録によるとビッグバンドが1セットとストリングスとその他の1ユニットで編成されています。ビッグバンドはご存知の通り、トランペットが4、トロボーンが4、サックスが5、加えてリズム・セクションとしてピアノ、ベース、ドラム、ギターです。
ストリングスは、バイオリンが10、ビオラとチェロがそれぞれ3、それにハープが1となっています。ところが録音を聴いてみると、2~3違う点に気が付きます。
まずこのアルバム全体を彩っている重要な楽器はフルートですが、僕が見た記録には書かれていません。普通ビッグバンド/JAZZの世界ではフルートはサックスの人が持ち替えて演奏する(特にアルト・サックスの人でクラリネットなど持ち替えるためサックス陣のことをReedsなども表現します)ので、サックスがフルートを兼ねている訳です。しかもバンドは1流プレイヤー達ですから間違いないと思います。
また、ハープは数曲の一部分に使われていますが、似たような音で記載されていない楽器に、チェレスタ(セレスタ)もあるように聞こえます。
一部分で使われており、一瞬、木琴かハープとギターの仕業かとも思いましたが、おそらく間違いないでしょう。
また、これはピアノのような楽器なのでピアノの人が弾いているのかも知れません。
ちなみに、このピアノはご存知ビル・ミラーです。
この編成に関する詳細は、僕にとっては、シナトラの録音を聴くことに必要な要素です。まさに“コンビの仕事”そのものだからです。
そしてそれ以上に、ネルソン・リドルのあの豪華で、キラキラしてワクワクさせられ、記憶に残ってしまうサウンド/アレンジを産み出すのにも欠かせない要素ですし、まさに歴史的には、アメリカのポピュラー音楽の一つの形式そのものなんだと思います。
そして「R/ヘフティ版」では、ビッグバンドが1セットだけです。これはシナトラのアルバムや演奏、そしてアレンジャーの歴史を知る上で大変重要な要素です。別で機会があれば詳しく触れたいですが、例えば1950年代のカウント・ベイシー楽団の成長・変化と近代化(モダンな音・編曲のバンドにする)欠かせない役割を果たしたのは、まさにこのニール・ヘフティですが、その彼を起用してシナトラ達が彼にやって欲しかったこと(あるいは彼がシナトラという舞台でやりたかったこと)は、まさに“モダンなサウンドのビッグバンドとシナトラ”だったのではないでしょうか。具体的な編成は、トランペットが4、トロボーンが4、サックスが5、リズム・セクションのピアノ、ベース、ドラム、ギターです。詳細な記録が手元にないのですが、ライナー・ノーツ等を見て(また実際聴いてみて)分かるのは、ベン・ウェブスターやコンテ・キャンドリなど大物や一流のジャズ・ミュージシャンが参加しています。
ところで、この編成と録音について気になる面白い点が3つあります。
1つは、シナトラの録音やライブではピアノはいつもあり、常にそれはビル・ミラーです(一時期を除き)。ところがこのアルバムをよく聴いてみてください。ピアノはほとんど弾いていません(聞こえません)、2曲を除いて。ニール・ヘフティは、なんとかビッグバンドだけで、シナトラとバンドのサウンドのコンビネーションを表現したかったのでしょう。
しかし、これはかなり珍しいことだと思います。メイキングを聴くとピアノが入っていない曲の時にも、曲が始まる前などにピアノの音がしていて、シナトラに音のサポートをしていたりする場面があるので、おそらくは、ビル・ミラーはスタジオにいたのでしょう。
しかしアレンジ上は、基本的に弾かないことになっていたのだと思います。
2つ目は、当時の50年代のカウント・ベイシー楽団はトロボーンが3本だったので、ニール・ヘフティのアレンジもトロボーンが3本でした(という印象があります)。
しかしここでは通常のビッグ・バンド編成に近く、トロンボーンは4本です。
これは音楽的には大変重要で、ビッグバンドとJAZZのサウンドをきちんと出そうとするとコードとコード進行上、4本あった方が都合がいいからです。
そして3点目は、編成に関するライナー・ノーツの間違えの可能性です。
元々のアルバムのレコード版のライナー・ノーツにはこうあります:<5 Trombones, 5 Trumpets, 5 saxes and 4 rhythm>。
しかし先ほど書きました通り、トロンボーンとトランペットはそれぞれ“4本”のはずです。まず聴いてみて、コードやアレンジ上5本ではないこと、またニール・ヘフティのアレンジとしても5本を採用する可能性は低いことから、これは違うように考えます。
しかし自信がなかったので、僕はJack Cooperという専門家にも訊いてみました。
Jack Cooperさんは有名なサックス・プレイヤーで作曲家やバンド・リーダーでもあり、米国メンフィス大学の音楽コースの教授でもあります。
ジャックに、この録音のトロンボーンとトランペットが5本かを確認すると、こう返事が来ました。
<トロンボーンは4、トランペットは4です。通常通りサックスは5で、リズム・セクションは4です>とのこと。
そして付け加えて、<ハーモニーはクローズドで(♪和音のレンジがオクターブを超えず音が近いこと)>、<やはりカウント・ベイシーのサウンドに聞こえる>と教えてくれました。
ハーモニーがクローズドでカウント・ベイシーのように聞こえるというのは、僕としては重要な指摘で、やはりこのアルバムのアレンジがモダンでスウィングする、ニール・ヘフティのサウンドを全面に出したかったという、証左となる訳です。
楽器の編成が4本でも5本でもよいーーーー確かに最終的にはどちらでもよい気もしますが、僕にとってシナトラを聴くということは、彼らの仕事をきちんと可能な限りみんなで知ることだと思っています。
At Long Last Loveの実況中継
イントロ
これらを前提に、「At Long Last Love」を実際に録音を聴いてみます。
「R/ヘフティ版」のイントロは4小節で、曲全体を一貫して流れるバンドの伴奏パターンで始まります。このパターンは、サックスとトランペット、トロンボーン(ブラス群)のリズムの組合せ(ポリフォニック、ポリリズム)とも言うべき、単純ながら無駄がなくシンプルで素敵なアンサンブルです。
ブラス群にはミュート(消音器)がつけられています。
このアルバムでは、全体的にどの曲もこのミュートが多用されていて、少し変わったキラキラした音やこもった感じの優しい音を出すのですが、偶然なのか「C/リドル版」でも同じミュート(しかも同じ種類でトランペットはハーマン・ミュート、トロンボーンはカップ・ミュート)が使われています。
「C/リドル版」のイントロは、一回聴いただけでは分からない若干複雑なリズムのアンサンブルです。そしてよりネルソン・リドルのサウンドだなと思うのは、ミュートを使ったブラス群に加えて、フルートがやさしくサポートし、イントロの最後ではバス・クラリネットがリズムを刻みます。
ちなみにテレビ番組の『Chairman of the Board』では、「C/リドル版」のアレンジを少しテレビのオーケストラ編成用に変えているのか、ハモったトロンボーンが代用されています。(こちらの方が個人的には好きです。笑)
さてもう一つ重要なのは、ギターです。
これは、例えば、シナトラお抱えのアル・ヴィオラや、アントニオ・カルロス・ジョビンが共演する時のギターではなく、リズム・セクションの一パートとして、ただずっとコードの音を出しながらリズムを刻むだけのギターです(だいたい4ビートなのでずっと1小節4回のリズム)。
「R/ヘフティ版」ではステレオ録音なので右のスピーカーから聞こえてきます。
よく聴かないと聞こえてきませんが、確実にリズムを弾いています。そして実は、「C/リドル版」でもそれは同じで、モノラル録音ですが、後ろにギターの刻みが聞こえます。
そして重要なのは、おそらくこの録音でもそうなのですが、このギターの刻むタイミングが他のリズム・セクションの楽器、例えばビート、テンポ上で一番重要なベースや、バンド全体のタイミングより、少しだけ早いのです。
厳密にコンピューターで解析しても、たぶんほぼそうだと思います。
カウント・ベイシー楽団ではこのベイシー楽団を支えた名ギタリスト(フレディー・グリーン)がいますのでよく言われることですが、この“ほんの少しだけ早いギター”、“前に行くギター”が実はバンドのサウンドやノリ、そして歌い手の歌に大きく影響します。
その意味では、シナトラのほぼすべての作品・録音には必ずこのリズムのギターがいます。他の歌手は、組むビッグバンドやオーケストラ、アレンジャー次第でリズムのギターがいないことも多いですが、シナトラの場合は必ずいます。
これはおそらく、シナトラの作品や歌を作るのに欠かせない条件であったということです。(ぜひ、ヒマがあれば、このリズムのギターだけをずっと聴くというのをやってみてください・・・シナトラとミュージシャンが喜びます。笑)
1番の「A」パート
最初の8小節の「A」、<is it an earthquake ~ or merely the mock?>の部分は、「R/ヘフティ版」ではイントロの伴奏パターンがそのまま続きます。
ネルソン・リドルでは、この「At Long Last Love」のイントロは特徴的で、例えば、「I’ve Got The World On A String」のような豪華で忘れがたいイントロがあり、またイントロと歌の始まりが完全に分かれている場合も多いですが、曲全体を支配するイントロの伴奏パターンを歌が始まってもそのまま変えないのは、「R/ヘフティ版」のシンプルなビッグバンドのサウンドを感じさせるのには十分です。
また1970年代のシナトラのアルバムを紹介するNBCのTV番組(アルバムのジャケットのでかいパネルを吊るしてスタジオで歌う番組)では、『Sinatra and Swingin’ Brass』から「R/ヘフティ版」の「At Long Last Love」が取り上げられています。
その中で、この最初の歌詞の<Is it an earthquake or simply a shock?>の「Shock」の後で、ドラムが1発“バン!”と大きな音を出し、シナトラもそれに合わせてポーズを取る演出があります。
これは「R/ヘフティ版」のアルバムでの録音バージョンにはありません。実は、「C/リドル版」の2番で、おそらく歌詞の「earthquake/shock」の意味にあわせてバンドが大きなバッキングを入れるのですが、それと同じような演出の意図があるのでしょう。
番組では2番の同じ部分でシナトラは、円形ステージを思いっきり左足で蹴るように踏みます。“Shock”でドン!と。
シナトラのコンサートやTV番組では、アルバムの録音のアレンジのバージョンとは少し違う演出や構成をすることもありますが、僕にとっては、このドラムの1発やシナトラの振りが、何かネルソン・リドルとニール・ヘフティがシナトラによって融合されたような気がしてしまいます。
ちなみに、このNBCのTV番組では、ほかの曲との都合なのでしょうか、ビッグバンドの通常の編成にホルンが2本加わって(座って)います。
しかも本来はこの「R/ヘフティ版」の「At Long Last Love」ではホルンはいませんが、TV番組には2人が座っていて、しかもたまに吹いています。
しかし、聴いてみるに、ホルンの音はあまりしてないように聞こえますので、おそらく吹いたふりをさせられているのかも知れません。
1番の「B」パート
次の8小節の「B」、<Is it a cocktail ~ the real McCoy?>の部分は、「R/ヘフティ版」では同じ伴奏パターンが繰り返されます。
ここまで来ると、このリズムとコードと楽器のサウンドが強く印象付けられますが、なぜかシナトラのスウィングする“シナトラ唱法”とあわせてか、全く邪魔になりません。
シンプルで、曲と、歌手にあわせた、神業のようです。「C/リドル版」では初めてここで、リズム・セクションに加わって伴奏が入ります。
来ました!ネルソン・リドル・サウンドです。
つまりストリングスでのコードの提示です。いつも、このストリングスが曲の前半で厚みを持って静かに出て来るとき、曲の途中でストリングスがビッグバンドの間を縫って顔を出すとき、ここにネルソン・リドルがいるな!、と感じてしまいます。
そして<Or is what i feel the real ~>の部分で「R/ヘフティ版」でも「C/リドル版」でも、バンドのバッキングが入ります。
いずれも、<i feel>の後で1回、<the real>の後で1回です。歌詞やメロディー、全体の展開の都合上、重要な一瞬の間に何かバッキングを入れたくなりますが、ネルソン・リドルもニール・ヘフティもほぼ同じようなバッキングを入れています。
一番の要因としては、おそらくシナトラの歌い方と解釈上、シナトラはこの2つの単語の後で音を切るので、それに合わせて効果的なバッキングを入れたのだとは思います。
なおエラ・フィッツジェラルドの1978年のアルバムに、『Dream Dancing』というのがあります。
元々このアルバムは、1972年の『Ella Loves Cole』というエラ・フィッツジェラルドの新しいコール・ポーターの“ソング・ブック”として作られたものに、新しい録音をいくつか加えてリパッケージしたリニューアル版ですが、ここでアレンジャーを担当しているのはネルソン・リドルです。
そして、この中の「At Long Last Love」では、ネルソン・リドルは、同じ<Or is what i feel the real ~>の部分で、シナトラの「C/リドル版」と「R/ヘフティ版」と同じようなバッキングを入れています。
しかもエラは、彼女らしく、まったく歌詞を切らず繋げて歌っていますが、なぜかアレンジは、シナトラと同じバッキングが入るのです。
これは、ネルソン・リドルが、自分やニール・ヘフティが作ったアレンジのイメージを離れられないと言う可能性もあるし、この歌をそのように解釈しているという理由もあるだろうと思いますが、それだけシナトラとの仕事に何か重い意味があったように、僕は感じてしまいます。
1番の「A+」パート
続いて次の8小節の「A+」、<Is it for all time ~ only Asbury park?>の部分、つまり全体の1番の後半部分です。
「R/ヘフティ版」ではそれまでの伴奏パターンは同じですが、ブラス群とサックスで受け持つ部分が入れ替わっています。
ただそれだけなのに、ちょっと雰囲気が変わります。
しかも個人的には音が低すぎがしないかと思うほど、サックスのバッキングは音が低いです。
下手なビッグバンドだとあまり美しいハーモニーで聞こえてこないくらいの低さです。そして<Is it Granada ~>からは、ビッグバンドの良さを強調するかのようにトロンボーン4本で長い音でのコードが突然出てきて、まさに楽器をやっている人ならなおさら分かりますが、地味にオイシイところで、吹きどころ/聴きどころです。
実は、NBCのTV番組の「R/ヘフティ版」では、この部分でバス・トロンボーンが、アルバムの録音にはない、1人だけのバッキングを入れています。シナトラになぜか多いバス・トロンボーンの出番です。(だいたいはジョージ・ロバーツがやってますし、日本だと岡田さんです。笑)先ほど、NBCのTV番組のビッグバンドにはホルンがいて、ほとんど何もしてないかも知れないと言いましたが、この部分のコードは楽器が4本以上ないと効果的に出せないので、もしかすると、抜けたバス・トロンボーンの代わりにホルンが和音の一部を吹いているかもしれません。
「C/リドル版」では、この部分はネルソン・リドルらしいオーケストラ全体がリズム・セクションのようにリズムを刻むかと思えば、再びあのストリングスの和音が出て、前半の落ち着きを取り戻してくれます。
前に、「At Long Last Love」のこの「A+」の部分の後半が、「C」に向けて盛り上がるようにコード進行が変わると言いましたが、この<~ Granada i see or only Asbury ~>の2小節が、実質的におそらく4度上に転調し、かつその転調したキーの中でもリハーモナイズ(♪和音を一時的に基礎的なものからより変化があり且つ違和感のないものに置き換える)されている感じに聞こえ、洗練されている上に、何よりコール・ポーターらしい雰囲気を表すコード進行上の要素として、この曲で一番重要な点となります。
その意味でやはりこの部分で、「R/ヘフティ版」も「C/リドル版」も、きちんとコードの和音の響きを聞かせたいという感じがします。
1番の「C」パート
そして1番最後の8小節の「C」、<Is it a fancy ~ at long last love?>の部分です。
「R/ヘフティ版」で、この<fancy>の部分ではバンド全体での伴奏が入りますが、コードもコード進行も、リズムも、フレーズも、個人的にはこのアレンジの中で一番すごい部分のひとつだと思います。
と言うのは、一番盛り上がる部分でどう曲のアレンジをするかは重要なキモで、歌を邪魔せず、しかしバンドやアレンジの良さを表現することは難しいからですが、ここでは全体で動きのある伴奏を歌に被せています。
他の部分にもありますが、フレーズのコードの一部をリハーモナイズしたり、また譜面には書ききれない/譜面だけでは表現できないフレーズや吹き方となっていて、なんともビッグバンドぽい響きです。
たぶんビッグバンドだけのリハーサルでは、この部分で突っ込んだ練習や指示があったように思います。(もちろん超一流のプロ・ミュージシャンなので時間はかからないと思いますが。笑)そして、この大き目の音で入る伴奏は、途中で小さくなり(デクレッシェンド)、また最後の<~ at long last love?>で2番に向けて大きくなっていく(クレッシェンド)ので、この「C」の8小節を全体として1つのパートとして捉えるアレンジの意図を感じます。
シナトラの歌も、アレンジと同じように8小節全体を長く大きなフレーズ感で捉え、メロディーを流れるように歌い、かつ、気楽にリラックスしながらも丁寧に歌っているように感じます。(そう、リズムを刻む前のめりなギターもお忘れなく。笑)
そして実は、ここで、ニール・ヘフティの(あるいはアレンジャーの)特徴的なもう一つの腕の見せどころが出てきます。
<is it at long ~>とシナトラの歌が出たところで、後ろにサックスの伴奏のメロディーが同時に聞こえますが、これはサックス5本が同じ音で(♪ユニゾン)、歌のメロディーに被せる伴奏となっています。
しかもこのサックスの流れは、転調した後の2番の前半まで、ずっと続いていきます。つまり、意味や主張を強くは感じさせないが、明らかにもう一つのメロディーだと感じさせるフレーズが、ユニゾンで歌と同時に被されて流れている(♪対位法、カウンター・ポイント)のです。
なお、「R/ヘフティ版」で歌われるNBCのTV番組を見ると、シナトラは、この1番の最後の歌詞を<is it at long ~>まで歌い、< ~last love?>を歌いません。しかも、いつものいたずらっ子のような表情で、ニヤついています。
この歌の歌詞とアレンジの構成を考えると、ずっと最後まで疑問形のままで進み、ようやく最後に答えらしい<at long last love>が出て来るのですが、1番の最後ではそれをあえて言わず、2番の最後の最後まで取っておく、という意味がありそうです。この歌詞全体の意図からすると、<at long last love>それ自体も答えではないかも知れないし、そもそも疑問を投げかけ続けるコール・ポーターらしい内省ぷりをよく表す曲なので、シナトラはそういった意図を組んで最後までその言葉を言わず、「どう思う?なんだと思う?」と、演出を兼ねた疑問を示したかったのかも知れません。
2番の「A」パート
さて、これから盛り上がる2番に入ります。1番の最後の1小節でBbからBに転調します。
2番の最初の8小節の「A」は、「R/ヘフティ版」では先ほどの対旋律のユニゾンのサックスがそのまま続き、しかもずっとほぼ同じ2小節単位のメロディーを吹き続けます。
この対旋律とも言うべき、繰り返される2小節のメロディーは、最後のところの音が1~2つ違うだけで他は同じ音です。
コード進行が変わっていっても、同じ音や同じメロディーが使えることを発見するのは、色々なJAZZミュージシャンやアレンジャーにとって結構嬉しいものです。
この2小節のメロディーでは、6度の音を強調しています(主音=トニックに対して6番目の音、ドレミファ~で言うとラの音、このアレンジの調Bで言うとG#)。これは、僕が参加しているSINATRA SOCIETY OF JAPANというシナトラのファンクラブがあり、そこの会報誌に書いた「Mack The Knife」と同じように、また、コール・ポーターの曲がちょっと悲しいように聞こえる理由でもありますが、長調の主音に対して6度の音から始まる=3度下の音から始まる音と音階は、長調の裏返しとして短調の悲しい感じのメロディーとなります(平行調)。
そういう雰囲気を出すために、コール・ポーターも、ニール・ヘフティも6度の音やその音階を意識して使っているのだと思います。
「C/リドル版」では<good turtle soup>の後に、一瞬、サックスのユニゾンのかわいいパッセージがあります。
なにかスープをイメージしているのでしょうか、ネルソン・リドル的なおしゃれさです。ちなみに「C/リドル版」ではユニゾンはここ以外ほぼ現れません。
ところで、この対旋律的なユニゾンは、まさに、ニール・ヘフティの得意な、そして一番シンプルだけど一番難しい、プロのアレンジャーの仕事だと思います。
シナトラのアレンジャーでこの手法を多用するのは、ビリー・メイです。一方で、ガンガンこれでもかと和音を被せてくるのは、ネルソン・リドルもその一人ですが、例えばゴードン・ジェンキンスですね。(ドン・コスタは両方でしょう。笑)
ちなみに、ニール・ヘフティのユニゾン好き、あるいはアレンジ手法の基礎は、彼自身がトランペットや作曲とアレンジを務めていた、初期のウッディー・ハーマン楽団にいた時に形作られたのではないかと思います。
彼は、当時すでにある意味で他のビッグバンドに対する差別化としてモダンだった、ウッディー・ハーマンのサウンドを作るのに貢献し、作曲やアレンジも手掛けています。
効果的なユニゾンが結構使われていますし、物の本によれば、ロシア/ソ連のクラシックの作曲家であるストラヴィンスキーに「エボニー協奏曲」という変わったJAZZぽい小品を作らせたのは、ウッディー・ハーマン楽団の有名な曲「Caldonia」のユニゾン・フレーズだったとも言われています。
ちなみに僕の印象では、他の有名なビッグバンドでこのユニゾン(または旋法)を多用してくるのは、歴史的にはビル・ホルマンやボブ・フローレンスだと思います。
あるいはソリストだと、ビル・エバンスやなどの系統です。
僕はこれを、和音と和声進行と対位法の凌ぎ合いだと思っており、クラシックに例えて、“JAZZにおけるロマン派のバロック回帰”、と呼んでいます。
2番の「B」パート
2番の次の8小節の「B」、<Is it a cocktail ~ the real McCoy?>は、「R/ヘフティ版」では、引き続き対旋律のユニゾンのサックスが2小節のメロディーを2回繰り返します(4小節)。
そして、ここも実は隠れた聴きどころですが、<Or is what i feel the real McCoy?>の部分で、<feel~>と<real>の後にブラス群が長めの音を2回鳴らします。
この2つの音のサウンドが最高にバランスよく、美しく、しかも粘りのある引っ張りが利いていてビッグバンドぽいです。
さらに、特にこの2回目の<real>の後のコードがリハーモナイズされて(♪おそらく経過的なディミニッシュ)おり、モダンな盛り上がりと変化を演出しています。
「C/リドル版」ではいつものネルソン・リドル風のバンド全体でのリズム・セクション化が起こり、エンディングに向けて盛り上がりをつけていきます。
2番の「A+」パート
そして2番後半の「A+」の8小節、<Is it for all time ~ only Asbury park?>です。
「R/ヘフティ版」では、またしつこく対旋律のサックスがユニゾンのまま2小節のメロディーを2回吹きます。
この同じパターンの繰り返しは、盛り上がりには欠かせない技法です。
また、よく聞いてみてください。前の「A」「B」も同じですが、このサックスの対旋律のメロディーとセットで、ずっとブラス群が一発、音を吹いています。
これは、「A」「B」部分ではトロンボーンだけ、「A+」部分ではトロンボーンにトランペットが加わります。
これだけの変化ですが、雰囲気は全く変わるものです。
そして、若干専門的・主観的ですが、この1発の音が、かなり長いように感じます。
別にこれは、この録音やニール・ヘフティに限ったことではありませんし、ネルソン・リドルにも感じることです。
そしてバンド・リーダーやアレンジャーの趣味もあるでしょうが、概ね良いビッグバンドでは、きもちこのような重要な音が長めにしっかりと鳴らされるものです。
もちろん編集上の調整、演奏の仕方、テンポなどにもよるでしょうが、余韻が残るというよりは、後ろに引っ張られる感じで、きちんとコードの響きを聞かせるかのような、そういう意図を感じる長さに聞こえる訳です。
おそらく譜面上は八分音符(=♪)でしょうが、聞いているとそれよりは長く、しかし八分音符の倍の四分音符(=♩)よりは短い感じがします。
またこの1発のようなバッキングは、その小節の最後にある時、その小節のコードではなく、その次の小節のコードを先取りして鳴らすものです。
それがより進んでいる、ワクワク/ゾクゾク感を出すのだと思います。
部分的な転調や変化を付けるコード進行上の要素として、この「A+」の後半の4 小節<~ Granada i see or only Asbury Park ~>が重要だと言いましたが、「R/ヘフティ版」では、この重要な部分を少ないビッグバンドの編成だけで盛り上げていく“ユニゾンの魔法”を使っているように聞こえます。
ニール・ヘフティは、トロンボーンにコードの和音を短く刻ませながら、この部分での一番重要な音を1つ選びます。
この音はC#(♪ドのシャープ)で、この部分の一時的な転調の中でも、そして、そのあと<~Park>で元の調に戻った後でも、効いてくる同じ音ですが、それをまずユニゾンでサックス群に長く吹かせ、続けてその上にまた同じ音を1オクターブ上のユニゾンでトランペット3本に吹かせ、最後に<~Park>のところで同じ音をさらに1オクターブ上(サックスから見ると2オクターブ上)でリード・トランペット1本に吹かせ、この音だけをユニゾンで3小節に亘り強調します。
そして1つの音をユニゾンのままオクターブで重ねていき、シナトラが同じ音で<Park>と歌った瞬間に、リード・トランペット1本がそれに応えるかのように、3回目の同じ音を鳴らすーーーただそれだけなのですが、これは、余計な音を出さず、無駄を省き、シンプルながら、最高に盛り上げることができる、まるで“魔法”のようです。そしてその後は、一瞬お休みしていたトロンボーンが、歌の間隙を埋めるかのようにパンチの利いたコードの和音で強くアタックして、ダウン(音を繋げながら下げる)します。まさに“ノックダウン”でやられた、と言う感じです(笑)。
ここの部分のシナトラは、この手の歌の中でも、最高にノッていて、ゾクゾクさせられます。
まさにビッグバンドとアレンジとシナトラの競演と言えます。
「C/リドル版」は、いつものネルソン・リドル風のオーケストラ全体でリズムを産み出すアレンジとなっていて、最後のエンディングに向けて押しまくるようなサウンドとなっています。
「C/リドル版」では、2番の「A」「B」「A+」の部分で、シナトラは必ずやることがいくつかあります。まずほぼすべての録音やライブで、「B」の終わりの<~ the real McCoy?>から、「A+」の最初の<Is it for all time or ~>に入る間は、息継ぎをせずに歌い続けます。
これは、「C/リドル版」のアルバムの録音も、イントロからいきなり2番に飛びエラ・フィッツジェラルドとデュエットする『The Man And His Music』のTV番組でも、先ほど紹介したテレビ番組の『Chairman of the Board』でも、それから、レッド・ノーヴォのコンボと一緒にワールドツアーしたライブ録音でも(これは「C/リドル版」をコンボ用にリ・アレンジしていることもあり)同じで、息継ぎをしません。
確かに歌手的には、こういう流れるところは息継ぎをせずに、つまりメロディーの流れを止めずに次の場面に入りたいものです。
また2番では、<the good turtle soup>の歌詞のgoodは”fine”に、<Is it a cocktail>のcocktailは“whiskey”に変えて、歌われることが多いです。
2番の「C」パート
ついに、最後の8小節の2番の「C」、<Is it a fancy ~ at long last love?>からエンディングの部分です(もう終わりますよ。笑)。
「R/ヘフティ版」では、前半の4小節<Is it a fancy not worth thinking of?>で、このアレンジで初めてビッグバンド全体が大きめの音とフレーズできちんと一緒に伴奏をします。
ただ厳密には、ブラス群とサックス群で微妙に音型/リズムが異なり、トロンボーン等がポルタメント(音を滑らかに繋げる)するなど、伴奏のフレーズの中でかなり色々な変化があります。
これは実はすごく重要な要素で、「R/ヘフティ版」の、スイングしたJAZZぽく、そしてキラキラしたサウンドを産むことに、大きく役立っています。
そして<Is it at long last>の部分で、サックスが後ろでバッキングを入れていますが、どうしてニール・ヘフティがこういう邪魔にならず且つ印象深いフレーズを思いつき、またビッグバンドも確実にこれを吹きこなすのかと思うほど、小さいけれど隠れた素晴らしい部分です。
最後の重要な歌詞をシナトラが歌い上げるところで、コードのハーモニーを押し出しつつも、逆に意識されるような対旋律のユニゾンでないものを採用し、しかも譜面で書いても吹きこなせないような感じです。
JAZZの楽器の特殊な奏法に「ターン」(装飾音的に一瞬音を上下にクルっと回転させる:譜面での表記はSを横にした形)がありますが、ここのサックスのフレーズは、ターン尽くしです。
しかもすごいのは、このターンを、サックス5本がハーモニーの中で違う音で吹いていて、かつターン自体もズレずにほぼハモっているのです。これは実にすごいことです。
ついに<~love?>の後はエンディングの伴奏に進みますが、最後の最後で、曲の最初の<Is it an earthquake>のメロディーがリフレインのように、途中までサックスによって、またしてもユニゾンで吹かれます。
しかも<earthquake>の“earth”の部分までです。
これはもう、ニール・ヘフティが曲と歌詞の意図を十分に理解した上で、洒落のようにアレンジしたのだろうと思います。
つまり ―― 説明してしまうと色気もないのですが ―― 、曲の重要なフレーズを再現するという技法の話と言うよりは、この曲の歌詞が極端な疑問形の集まりであり、その答えはシナトラが示したように「どう思う?」というところまでで、ニール・ヘフティが、アレンジを通じて、もう一度最後にその疑問文の最初を示し、しかもメロディーを完結させずに途中でやめることで、まだまだ疑問は終わらず答えは出ない、ということを印象付けたかったのでしょう。
そしてエンディング・ノートは、JAZZぽいテンション(ドミソの上に不協和音を乗せる)がたくさん乗っかったコードで締めくくられます。
疑問形のサックスと、このJAZZ的なブラス群のコードが相まって、洒落たビッグバンド的な終わり方となります。
「C/リドル版」では、ビッグバンド/オーケストラ全体が同じ伴奏を大きめのフォルテの音と強烈な強さのリズムで演奏し、エンディングへと突き進みます。
まさにCapitol時代に多いネルソン・リドル風のリズム化したアレンジとサウンドで、やはりこういう時のシナトラとのコンビは迫るものがあり、よりシナトラの歌と歌い方とアレンジとオーケストラの演奏が、すべて一体となって聞こえてくる気がします。
つまりネルソン・リドルが、シナトラの個性やスタイルを完全に理解した上で、オーケストラ全体をあたかもピアノで弾いてサポートしているような状態だと感じます。
シナトラのこの録音がモノラルで古いために、一見(一聴)すると分かりにくいのですが、よく聴くと、オーケストラも相当に大変そうなくらいの強さと大きさ演奏しているのが分かり、特にドラムは最大限の強さでノリノリで叩いていることが伝わってきます。
もし、願うならば、1963年にシナトラが過去のネルソン・リドルがアレンジした曲を中心に、新たなオーケストラで再録音したアルバム、『Sinatra’s Sinatra』に、この「At Long Last Love」を入れて欲しかったと思います―――同じくコール・ポーターの「I’ve Got You Under My Skin」のように。
シナトラの挑戦と創造性
フランク・シナトラのReprise時代の最初のアルバムは、ジョニー・マンデルがアレンジを担当した『Ring-a-ding-ding』です。このアルバムは1961年のリリースですが、まだCapitolとの契約が残っていた前年の1960年末から録音が始められているとのことです。
このアルバムを皮切りに、シナトラの新しい時代のアルバム―――シナトラの歌い方や解釈、曲の選曲からビッグバンド/オーケストラのアレンジとサウンドまでが、その前と比べて相対的に、あるいは革新的に、変化を遂げたアルバムが立て続けに産まれました。
特に1961年の『Ring-a-ding-ding』(ジョニー・マンデル)と『Swing Along With Me』(ビリー・メイ)から、1964年の『I Remember Tommy』(サイ・オリバー)と『It Might As Well Be Swing』(クインシー・ジョーンズ)までの4年間は、シナトラと多くのアレンジャー達の挑戦の時期であり、その後のシナトラの約30年を支える“お決まり”を創り出した、10を超える傑作のアルバムが量産された時期でもありました。
ご存知のように、1965年に『September Of My Years』(ゴードン・ジェンキンス:2回目のアレンジ)の新しいサウンドで、グラミー賞を獲り、翌年以降に「Strangers in the night」や「My Way」のビッグヒットが産まれ、60年代を終え、休養を経た後、70年代以降も新たな曲・スタイル、そしてアレンジとサウンドに挑戦し続けました。
そう考えると、大雑把に、いやもちろん確かに、シナトラはアメリカのポピュラー音楽の歴史そのものだとも言えますが、より僕の「シナトラ体験」としての思いを込めて言えば、この新旧のビッグバンドのアレンジとサウンドが混ざり合いながらも変わっていく―――もちろん現時点から現在進行形として見れば、全てがいつでも新鮮で、どれもが素晴らしい―――この60年代最初の数年間の“仕事”が、実に挑戦的で意欲に満ちた創造性を感じさせ、また未だに僕に最高の「シナトラ体験」を与えてくれているように思います。
(文:DnDマーケティング株式会社代表取締役 / アマチュアジャズシンガー 野口龍彦 編集:濱田真秀)